-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
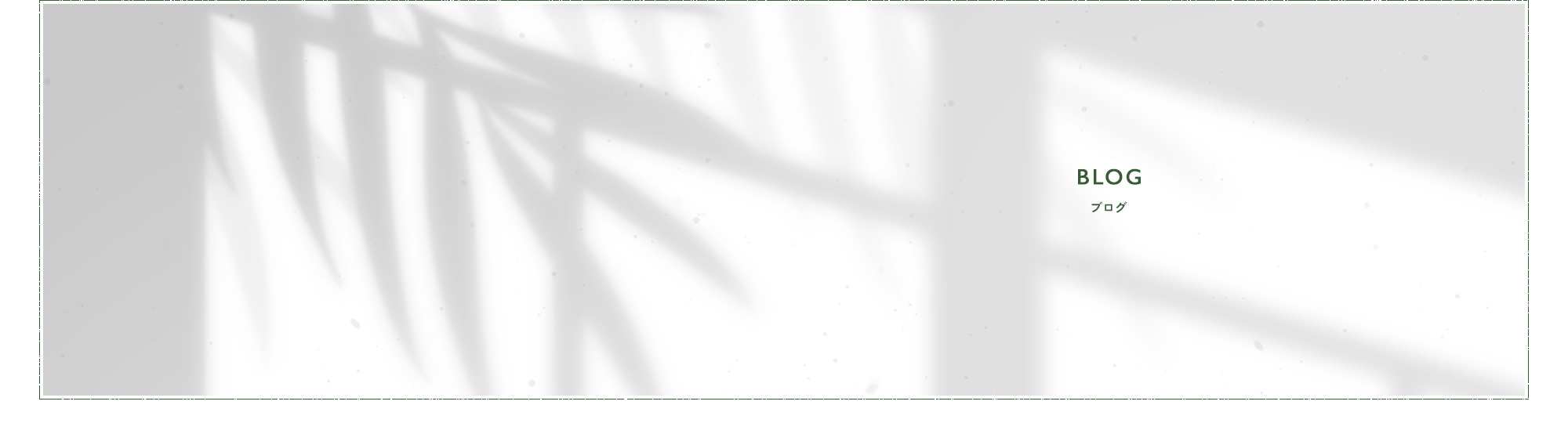
皆さんこんにちは!
看護ステーションUru -ウル-、更新担当の中西です。
さて今回は
~支援計画~
ということで、訪問看護における支援計画の意義、作成の流れ、活用のポイントを、現場目線で深く掘り下げてご紹介します。
「その人らしい生活」を支えるための設計図
高齢化や在宅療養ニーズの高まりにより、訪問看護の役割は年々重要性を増しています。
その中で、看護師が日々のケアを的確に、かつ継続的に行うために欠かせないのが「訪問看護計画書(支援計画)」です。
これは単なる事務書類ではなく、ご利用者の生命・生活・尊厳を守るための“看護の道しるべ”。
目次
訪問看護計画とは、ご利用者の病状・生活背景・目標に基づいて、
「どのような看護を、どのくらいの頻度で、どのような方法で提供するか」を具体的に記した個別支援の設計図です。
ご利用者の生活の質(QOL)を向上させるための看護実践の道筋を明確にする
多職種(医師・ケアマネ・介護職など)との連携を円滑にする
看護師間での情報共有をスムーズにし、支援の質を担保する
ご利用者・家族が安心して在宅生活を送るための見通しを提供する
📌 計画なき看護は、“その場しのぎの対応”になり、事故・混乱・不信感を招く可能性があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| アセスメント | ご利用者の健康状態・生活状況・ADL・家族の支援体制などの評価 |
| 長期目標 | 「生活の中でどのような状態を目指すか」例:自立歩行、服薬管理の確立など |
| 短期目標 | 長期目標に向けたステップ、例:週2回のリハビリ実施、排泄パターンの安定など |
| 実施内容 | バイタル測定、創傷処置、清潔ケア、服薬管理、リハビリ、精神的ケアなど |
| 期間・頻度 | 訪問の回数、期間、再評価のタイミング |
| 担当看護師 | 主担当者とサポートスタッフの役割明記 |
| 関連職種 | ケアマネ、主治医、理学療法士、薬剤師などとの連携内容 |
📌 「誰が見ても、何を、どのように支援するのかが明確になる」ことが重要です。
複数の看護師が交代で訪問する中でも、計画があれば看護内容のズレを防ぎ、一貫性のある支援が可能になります。
医師の指示書だけでは把握しきれない日常生活の課題や本人の希望を支援計画でカバー。
→ 例:「夜間のトイレ回数が多く、転倒リスクがある」など、生活に即した視点が活きる。
「今、何のために何をしているのか」が伝わることで、不安が軽減され、協力体制が築きやすくなります。
急変時や退院・転院、引き継ぎ時にも、支援計画があればスムーズな対応と正確な情報伝達が可能。
初回訪問での観察・面談・ご本人の希望の聞き取り
主治医の指示書、ケアマネのケアプランの確認
家族構成・生活環境・本人の価値観も重要な情報
📌 アセスメントの質が、その後の目標設定と看護内容の的確さに直結します。
「この人らしい生活とは何か?」という視点で目標を設定
数値化・行動化された目標が望ましい(例:1人で歩いてトイレに行けるようになる)
実施項目は「観察・処置・相談・指導・予防・連携」の視点でバランスよく
ご本人の負担にならないスケジュール調整も大切
作成した支援計画はご本人・ご家族と丁寧に共有し、納得と合意を得ることが重要
必要に応じて、ケアマネジャー・主治医と再調整
月1回~3か月に1回を目安に目標の達成状況・状態変化を踏まえて再評価
状態悪化や介護負担の変化があれば、即時更新
📌 計画は「一度書いたら終わり」ではなく、“生きた書類”として随時見直しが必要です。
訪問看護における支援計画は、単なる業務指示書ではなく、
「その人が、その人らしく、安心して暮らしていけるように支える計画」です。
✔ 支援の一貫性
✔ チームの連携
✔ ご本人の納得
✔ 緊急時の備え
これらすべてが、丁寧に作られた支援計画によって支えられているのです。
看護師として、目の前の人の暮らしと命に寄り添うために。
支援計画を「ただの書類」から「信頼の証」へと高めていくことが、専門職としての力となります。
| 項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 情報収集 | 状態、希望、家族状況、関係者情報が網羅されているか |
| 目標設定 | 長期・短期ともに具体的で、現実的か |
| 看護内容 | 必要かつ過不足ない支援項目になっているか |
| 実施体制 | 担当者・頻度・時間配分が明確か |
| 共有 | ご本人・家族・多職種との情報共有が行われているか |
| 見直し | モニタリング・再評価の仕組みがあるか |
看護ステーションUru -ウル-では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()